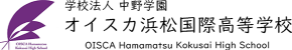【環境教育】ヘチマ和紙で地域おこし~新聞掲載~
2025.2.17(月)
先日、本校で行ったヘチマ和紙づくり。この取り組みが新聞に掲載されましたので紹介します。
2025年2月12日(水) 中日新聞掲載

ヘチマ和紙で地域おこし
商品化へ浜松・庄内住民ら取り組み 試作実験に児童生徒ら参加
かつて浜松市で栽培が盛んだったヘチマを活用し、地域の活性化を図ろうと、庄内半島の住民たちが和紙の原材料にヘチマを加えた紙を作り、地域の新たな特産品を開発する取り組みを1月に始めた。混入割合を変化させる実験を繰り返し、できる紙の質感を確認。地元の児童生徒のアイデアも取り入れて、来年度の商品化を目指す。 (志方一雄)
取り組みは、庄内半島の活性化を目指す市民団体「浜名湖庄内半島ドリームプロジェクト」の下部組織「へちま×和紙実行委員会」(須山嘉七郎(すやまかしちろう)委員長)が担当。人口減が続く庄内半島の活性化には、新たな地域ブランドの開発が必要と考え、市の地域力向上事業にも採択された。
ヘチマを加えることで紙の強度が高まるが、ヘチマを活用した紙づくりは全国でも例がないという。「へちま和紙」は、卒業証書やランプシェード、壁紙などへの活用が想定される。
ヘチマ栽培の普及を目指す浜松市の団体「浜松へちま・ミライ」も取り組みに協力。地元の庄内学園の小中学生やオイスカ浜松国際高校の生徒も加わり、各学校などでも計6日間かけて、ヘチマの割合を10~90%に変化させる実験を繰り返す。須山委員長は「魅力ある地域づくりには、地元の子どもたちも関わってもらって商品化を進めることが大切」と話している。
8日に庄内協働センターで実施した実験には地元の小学生や大人たち10人ほどが参加。和紙の原料のコウゾとトロロアオイにヘチマを10%混ぜ、紙をすいて乾燥させる作業を繰り返した。参加した庄内学園5年の井出さんは「できた紙を見て、何が作れるのかを考えるのが楽しい。筆箱を作るといいかも」と話していた。
商品化へ浜松・庄内住民ら取り組み 試作実験に児童生徒ら参加
かつて浜松市で栽培が盛んだったヘチマを活用し、地域の活性化を図ろうと、庄内半島の住民たちが和紙の原材料にヘチマを加えた紙を作り、地域の新たな特産品を開発する取り組みを1月に始めた。混入割合を変化させる実験を繰り返し、できる紙の質感を確認。地元の児童生徒のアイデアも取り入れて、来年度の商品化を目指す。 (志方一雄)
取り組みは、庄内半島の活性化を目指す市民団体「浜名湖庄内半島ドリームプロジェクト」の下部組織「へちま×和紙実行委員会」(須山嘉七郎(すやまかしちろう)委員長)が担当。人口減が続く庄内半島の活性化には、新たな地域ブランドの開発が必要と考え、市の地域力向上事業にも採択された。
ヘチマを加えることで紙の強度が高まるが、ヘチマを活用した紙づくりは全国でも例がないという。「へちま和紙」は、卒業証書やランプシェード、壁紙などへの活用が想定される。
ヘチマ栽培の普及を目指す浜松市の団体「浜松へちま・ミライ」も取り組みに協力。地元の庄内学園の小中学生やオイスカ浜松国際高校の生徒も加わり、各学校などでも計6日間かけて、ヘチマの割合を10~90%に変化させる実験を繰り返す。須山委員長は「魅力ある地域づくりには、地元の子どもたちも関わってもらって商品化を進めることが大切」と話している。
8日に庄内協働センターで実施した実験には地元の小学生や大人たち10人ほどが参加。和紙の原料のコウゾとトロロアオイにヘチマを10%混ぜ、紙をすいて乾燥させる作業を繰り返した。参加した庄内学園5年の井出さんは「できた紙を見て、何が作れるのかを考えるのが楽しい。筆箱を作るといいかも」と話していた。